
養老孟司さんの「自然」と「意識」の話
日本の医学博士、解剖学者、東京大学名誉教授の養老孟司さんについて、今なお強烈に印象に残っていて人生のガイドラインの1つとなっているような話がある。
養老さんが解剖を行っていると、このぐらいの原因で何で死んだのかなと思う死体と、こんなボロボロの身体でよくこれほど長生きしたなと思う死体の2つがあるという。
軽々に言ってはいけないかもしれないが、どんなに煙草を吸おうが酒を吞んで無茶してもそれでも長生きする人はするし、いくら健康管理していたとしても人間はあっけなく死ぬこともある。確率で平均すれば、養生に努めた方が長生きするとは思う。しかし実際に、美人薄命だとも限らないし人の寿命は公平なわけでもない。「人間五十年 下天のうちを比ぶれば夢幻の如くなり 一度生を受け 滅せぬもののあるべきか」と織田信長も本能寺の変で舞っているではないか、そのような軽い無常観がずっと気持ちの奥底にある。そうは言っても太く短かく生きるというほどの覚悟もないけれど。
たまたま観た養老孟司さんのYouTube番組「自然の話」はとても面白かった。その中で人間は「実は自分が自然だっていうのをうっかりしちゃうと忘れちゃうんだ」と語っている。人間が自然である一番の典型は、身体で始めは直径0.2ミリの受精卵から生まれて、それから大人になった身体は全部食べたもので出来ている。人はつまり田畑から生まれたようなものだから、死んで土に還ると昔から言っている。
自然とは〈人の意識が作らなかったもの〉と定義し、意識的にしつらえたものは全部、人工。意識的(人工的)な究極は都市。都市は意識から全て造られている。要約すればそういうことであった。
その上、なんと意識って実は自らの主導権を持ってないのだ、と!
意識は自分が身体も動かしていると思っている。しかし朝、目が覚めるのも眠るのも、意識がやっているのではない。目が覚めると意識は自分がやっていると思っている。しかし——意識はいったいどこから出てくるか、それは「地下鉄の電車はどこから入れたの?」よりはるかに難しい。
「一番問題なのは、感覚から入るものが非常に限定されてしまっていることだ」と聴いて、得たりとばかり強く膝を打ち、その痛さで目が覚めた、ような気がした。



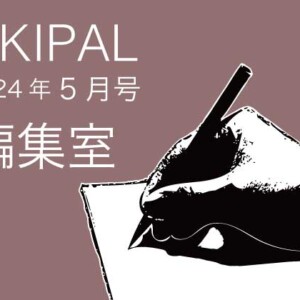



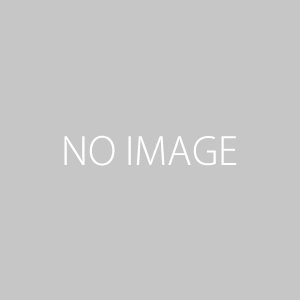



この記事へのコメントはありません。