
息もつかせぬ『ババヤガの夜』に、息を吞む
話題の王谷晶(おうたに あきら)著『ババヤガの夜』を読んだ。2025年、英国推理作家協会(CWA)が主催する ダガー賞(Dagger Award)翻訳部門 を受賞し、日本作品として初の快挙であった。評判通りのバイオレンスで、血の臭いがまとわりつくような描写で、息もつかせない。
「漫画や、音楽や、ファッションよりもそれ(暴力)がずっと楽しい娯楽、唯一の趣味」としてそだった新道依子が主人公。街で依子は関東有数の暴力組織内樹會と遭遇し、その腕っ節を見こまれて会長の一人娘、尚子の護衛役(ドライバー兼ボディーガード)として、死ぬか、護衛役を引き受けるかの二択でスカウトされる。美しくに生き人形のように育てれた尚子と、暴力にアイデンティティを見出しているかのような依子の関係は次第に少しずつ変化し、時に守る側、守られる側という関係性が反転していく。
内樹會幹部の柳が本音を漏らす場面がある。
「私が告げ口したら?」「誰がお前の言うことなんか信じると思う。この業界はな、こと信用においては聖母マリアさまより泥棒乞食でも男の方が上なんだよ」。依子は答える。「餓鬼じゃないんだよ。そんなことはとうの昔に知ってる。何が〝この業界〟だ。世の中みんなそうだろう」。柳は「ほう、若いのになかなか達観してんな。そうよ、この世はろくでもねぇ。何事も諦めが肝心だ」と言い放つ。
マイノリティとしての生きづらさ居場所のなさがあぶり出されているように思えて、この会話の場面がしばらく、記憶の中でループ再生されていた。ババヤガとは、スラヴ民話の「魔女」で人を取って喰う恐ろしい女。依子も尚子も「できるなら鬼婆になりたい」と言っていた。恐るべし〈鬼婆〉ではある。
『テルマ&ルイーズ』(1991年アメリカ・監督はリドリー・スコット)を連想してビデオで観たのだが、なんと34年前の作品でその長い年月に一瞬息を吞んだ。





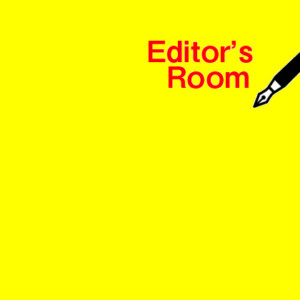





この記事へのコメントはありません。