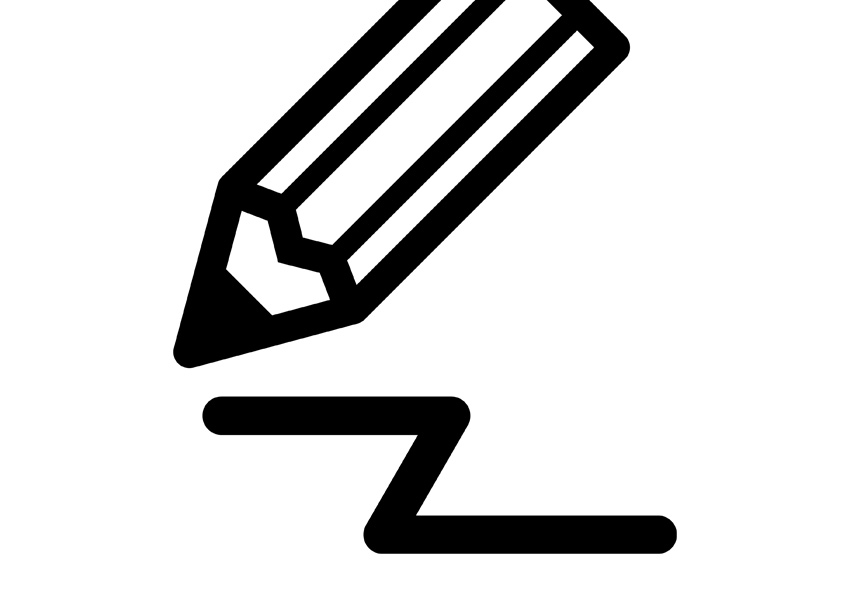
紙に始まり、神で終わる?
「紙でできることは何か?」「地方から何が発信できるか?」という問いを考えています。
このインターネット真っ盛りの今のご時世で、絶対紙だ、とこだわっているわけじゃないのです。
考えているのは高度商業流通社会にあって、館鼻岸壁朝市に人が集まるのは何でか?と似たような問いなのです。
TwitterやFacebookで伝えきれないことはあるのか? あるとすれば何なのか?
紙の方が伝わりやすい何かがあると漠然とでも感じているから、『UKIPAL』を作っているわけで。テキストも縦書きと横書きでは違うだろうし、どちらが良い悪いの話ではないでしょう。
先日、たまたま買ったままだった井田真木子『フォーカスな人たち』(新潮文庫)を読みました。これがなかなか自分にとって示唆に富む内容で、強く印象に残りました。
『FOCUS』というのはスキャンダラスな写真週刊誌の草分けで、1981年に創刊し2001年に休刊。井田真木子さんはフリーランスのライターとして活躍。2001年、将来を嘱望されたライターが44歳で若さで亡くなったという報道が記憶にあります。
その本で取り上げられているのは、黒木香、村西とおる(AV女優と監督)、太地喜和子(女優)、尾上縫(割烹女将)、細川護煕(元首相)と個人的にはさほど興味を抱かない人たちですが、読後の印象は強烈でした。結局のところこの主役は「バブルという時代」。そして経済的には破綻したけれども、「失われた」数十年を経た日本と日本人のマインドでは「バブルは終わっていない」という感慨がありました。
文中で
「私たちはせわしなくそのようなことを知りたがり、情報を拾っては捨て、捨てては拾った。情報への渇望は躁病を思わせるむやみなスピードでせりあがり、その欲求不満を一気に解決するツール、すなわちコンピューターが普及した一九八〇年代にいたり、高度情報化社会は本格的に時代の扉をひらいたのである」とあります。
さらに
「従来、雑誌における写真と文章の関係は、写真誌の逆である。わずかな例外をのぞき、文章が主で写真は従だ。文章が表現しきれない内容を写真が説明するということが常套手段だったのである。だから、その場にあったモノのすべてを露骨に記録してしまうカメラのあとを、文章が必死に追いかけて辻つま合わせに奔走するという、写真誌のスタイルは、それまでの常識をくつがえすものだった。この主従の逆転は、文章の性格と同時に、写真の性格も変えずにおかなかった」
とし、
カメラからも添えられた文章からも「表現性は奪われた」と続けるのです。
同時期に相次ぎ創刊されたビジュアル重視のファッション誌、情報誌もその構造のままで今に至ります。
決してそれを悪いと決めつけているのではありません。高度情報化がさらに加速した2016年現在、この地域社会でできることは何だろうと考えているだけです。
井田さんは書きました。
「1985年に「私たちの前に、とある〝神〟が降臨して、時代を俯瞰してみるきっかけを与えたのである。それは実に変わった名を持つ神だった。金融緩和政策。それが降臨した神の正式名称である」
私たちに降臨する神の名前は何なのでしょうか。
それにしても優れたライターを亡くしていたことに、あらためて残念な思いをさせられた1冊でした。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。





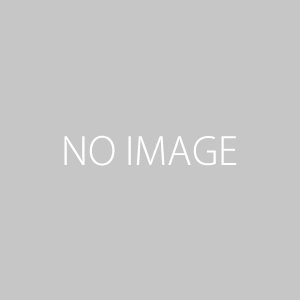





この記事へのコメントはありません。